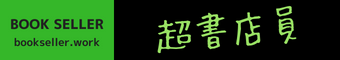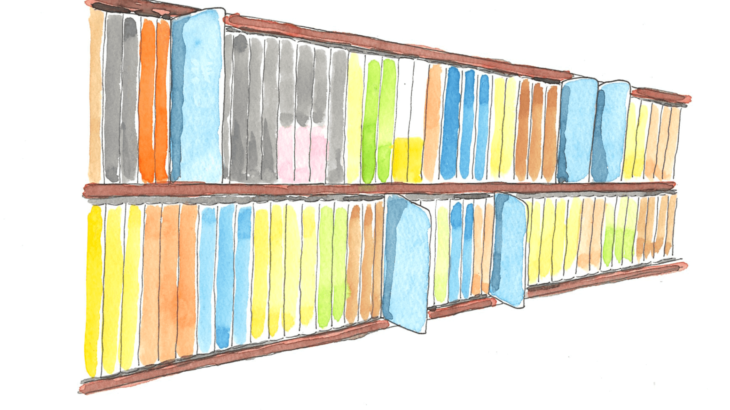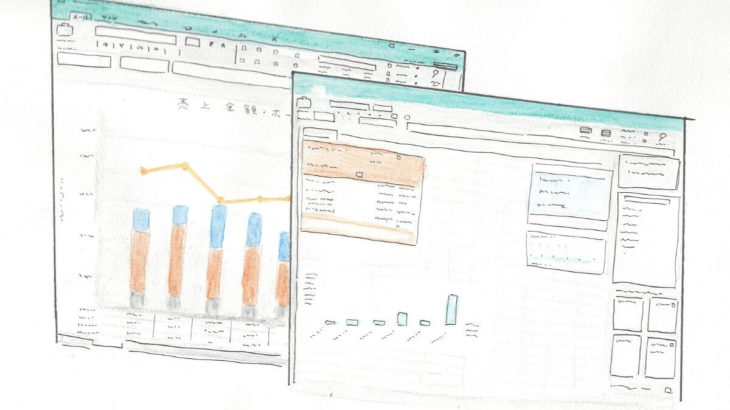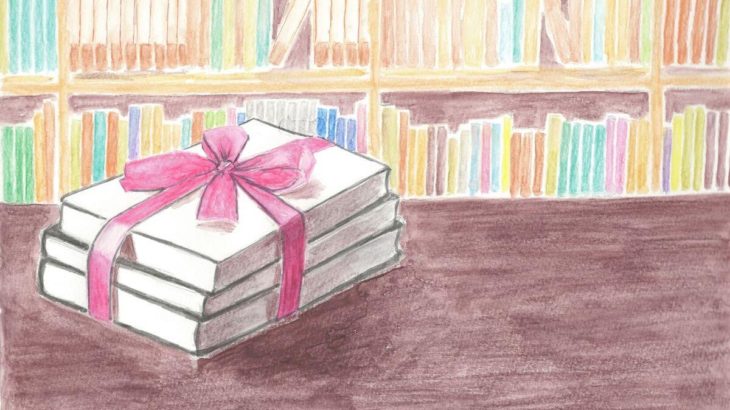書店員は棚卸についても理解を深めておく必要があります。
棚卸は、店舗の規模や会社によって定休日を作ったりして棚卸を自分達で行うところもあるでしょうし、全て棚卸業者に委託する書店もあるでしょう。
ただ多くの書店員は、「棚卸をやって終わり」「棚卸の数字を見て終わり」ひどい時には「棚卸準備大変だった、で終わり」という人がいます。もちろん会社として決算書類を作成するためにやっている側面もあるのですが、自店舗において棚卸結果の数字を活かせる要素は詰まっています。
まずは、棚卸結果の数字が何なのかを理解する必要があります。そこで棚卸とは何なのか、棚卸で出てきた数字が何なのかを簡単に説明したいと思います。数字を把握すると棚卸の重要性や、店舗の課題、今後の方針などもを決めていく指針になるはずです。
棚卸しとは何か
棚卸とは商品の在庫を数えて、売上に対する正確な利益を把握することです。
もちろん全ての在庫をPOS管理している書店であれば、在庫を一点一点数えるという面倒な作業をしなくても、仕入、販売、返品などの時間や金額は管理されていますので、データ上では最新のものがすぐに出るはずです。
とはいえそれはあくまで「データ上」という話です。当然そのデータは何も人為的な間違いがなく、店舗営業が正確に行われていれば、実体もデータ通りになります。
しかし、小売(書店)をやっている皆さんなら分かると思いますが、データと実体の在庫に差がないことなんてあり得ません。
入荷時の検品ミス、万引き、レジの打ち忘れなど、様々な要因がありますが、日々ズレる可能性をはらんでいます。
そこで、「実態」を把握する業務が「棚卸」です。
どの商品がいくつあるかを全てカウントすることで店舗の間違いない数字が表面化します。
棚卸結果で把握しなければいけない数字
① 在庫高(ざいこだか)
もっとも基本的で、かつ最重要の数字です。
在庫高とは、自店が保有している在庫の金額を指します。
つまり、あなたの店にどれだけ“お金が眠っているか”を示す数字です。
売れ筋本であっても、在庫が多すぎれば資金が滞留しますし、逆に在庫が少なければ機会損失になります。
この「在庫高」を正確に把握することが、店舗の健全性を知る第一歩です。
在庫高 = 現在庫数 × 仕入単価
この金額が前年よりも増えている場合、
・仕入れすぎ
・返品の遅れ
・売上減少
など、何らかの課題が隠れている可能性があります。棚卸後には、去年の在庫高と今年の在庫高をカテゴリごと比べてみてください。
② 在庫差異(ざいこさい)
棚卸で最も注目すべき数字が、この「差異」です。
差異とは、システム上の在庫(想定在庫)と実際の在庫(実在庫)のズレを意味します。
| 種類 | 説明 | 主な原因 |
|---|---|---|
| プラス差異 | 実在庫が想定在庫より多い | 登録漏れ、返品処理ミス |
| マイナス差異 | 実在庫が想定在庫より少ない | 万引き、レジ打ち忘れ、返品処理ミス |
この差異が大きいほど、「帳簿上の利益」と「実際の利益」が乖離することになります。
そして、基本的にはマイナス差異が出ることになり、それだけで利益が吹き飛びます。1冊足りないとその分を取り戻すのに6冊売らなければいけないのが書店という業態です。
20万円マイナス差異を取り戻すのに120万円の売上、50万円のマイナス差異を取り戻すのに300万円の売上です。棚卸の数字を見て「ふ~ん」では済まされない数字に見えてきたのではないでしょうか。
差異は「利益の穴」です。
棚卸は、その穴の大きさと場所を探す作業だと考えてください。
③ 差異率(さいりつ)
単純に差異額だけを見ても、規模の大きい店舗と小さい店舗では比較できません。
そこで重要なのが「差異率」です。
差異率(%)= 差異額 ÷ 在庫高 × 100
この数字を毎回の棚卸ごとに出しておくと、
・前回より差異率が下がった(改善)
・特定ジャンルだけ高い(原因が限定)
など、変化と傾向を分析できるようになります。
差異率が1%を超えてくるようなら、どこかにシステム的・人的な問題が潜んでいると考えるべきです。
これらを間然するための対策を考えるのと同時に、次回の棚卸に向けての差異率目標を掲げることは書店運営をしていく店長の仕事です。
棚卸の数字は「現場の健康診断」
棚卸の数字は、経理のための帳簿ではなく、現場を映す鏡です。
優秀な店長のお店の在庫のズレは少なく、スタッフへの統率のとれない店長のお店の在庫はズレまくります。
ですから、棚卸で出てきた数字を「経営資料」としてだけでなく、現場の改善ツールとして活かす意識が重要です。
在庫高が高すぎるなら、陳列効率や返品スピードを見直す。
差異率が高ければ、入荷・返品・会計のフローを精査し、万引き対策も考える。
つまり棚卸の数字は、店舗の“健康状態”を示す血液検査のようなものなのです。
もちろん、一店舗を一人で全て回している(スタッフ0人)書店はほとんどなく、組織で運営しています。棚卸で「差異が出た=誰かが悪い」ということではありません。
棚卸結果からから ” どの領域でロスが発生しているか ” を見極めることが大切です。
| 分類 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 人的要因 | レジ打ち忘れ、誤返品、誤陳列 | マニュアル再確認、複数チェック体制 |
| 物理的要因 | 万引き、破損、持ち出し | カメラ配置、声かけ、売場導線改善 |
| システム要因 | 登録ミス、スキャンエラー | 入荷・返品の自動照合システム導入 |
ロスの発生原因を正確に分類できるほど、改善策が現場レベルで具体化します。
棚卸から考える「在庫意識」の重要性
書店員が理解しておくべきことは、在庫は「モノ」ではなくお金であるということです。
売場に積まれた1冊1冊が、会社の資産であり、利益の源泉。
1冊の差異が積み重なれば、店舗の収支を簡単に変えてしまいます。
だからこそ、
-
棚卸を“作業”で終わらせない
-
数字の裏にある「原因」と「改善策」を探る
-
在庫を“管理する”のではなく、“守る”意識を持つ
この3点を、全員が共有していくことが大切です。
棚卸で差異をゼロに近づけるということは、単にお客様の探している本を見つけるスピードが上がるだけでなく、お金やお店を守り信頼を積み重ねることと同じです。
棚卸を“面倒な恒例行事”ではなく、自店の未来を整えるメンテナンス時間と捉え、数字の奥にある現場の真実を見つめ直していきましょう。